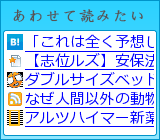ネットでは女神湖にも円筒分水があるという情報があるので、女神湖を一周して探してみたのですが見つけられませんでした。で、蓼科湖の円筒分水(茅野市)へ。ここも先に訪れた鷽ノ口円形分水とともにぜひ訪れてみたかった場所です。

蓼科湖の堰堤の下にあります(この写真は、堰堤の上から見下ろすカタチで撮ったものです)。場所はすぐにわかると思います。

説明書みたいなものがないので、この円筒分水についての詳細はサッパリわかりません。
右側の蓼科湖からの水を、手前右側と左奥二つの用水路に分水しているようです。なかなか近未来的な滑らかな造形をしている円筒分水です。
長野県内で訪れていない円筒分水は、(確実に存在しているとわかっているもので)あと1箇所となりました。
2011,05,25 撮影