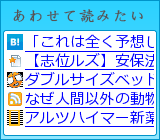鷽ノ口円形分水(佐久穂町)を堪能したあとは国道141号線に出て、北上。国道142号線を経て主要地方道40号線で南下。女神湖方面を目指しました。途中で、今回のツーリングの目的地のひとつである「鳴石」(立科町)に立ち寄りました。

ソフトクリームなどを販売している売店の駐車場から、北側に100mほど入った林の中にあります。「雨境峠祭祀遺跡群」のひとつで、ここで神の降臨を願ったりするなどの祭礼が行われたそうです。
- 「雨境峠祭祀遺跡群」・・・他に「鉤引石」・「賽の河原」・「与惣塚」・「法印塚」など
周辺では勾玉が多く出土したことから、このあたりは「勾玉原」とも呼ばれるとか。けっこう標高の高い場所ですが、大昔から人々が活動していたんですね~。

案内板のある方からすると裏側ということになるのですが、こちらのほうが不思議感があるので、ひょっとするとこちらが表側(祭祀に際して、人々が集う側)だったのではないかとも思ったのですが、どうだったのでしょう。
2011,05,25 撮影